未経験からタクシードライバーへ!二種免許取得の全知識と成功の秘訣
「タクシードライバーになりたいけれど、二種免許ってどうやって取るの?」「費用はどれくらいかかるの?」「年齢や経験がなくても大丈夫?」
このような疑問や不安を抱えている方は少なくありません。タクシードライバーとして新たなキャリアをスタートさせるためには、旅客運送に特化した「二種免許」の取得が必須です。しかし、その取得方法や試験内容、費用、期間について、具体的な情報が不足していると感じる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、未経験からタクシードライバーを目指す方のために、二種免許の基礎知識から取得条件、具体的な取得方法、費用、試験対策、さらには地理試験廃止後の最新情報まで、網羅的に解説します。また、年齢や経験に不安がある方でも安心して挑戦できるよう、タクシー会社のサポート体制や成功事例もご紹介。この記事を読めば、二種免許取得への具体的な道筋と、タクシードライバーとしてのキャリアの可能性を理解し、自信を持って次のステップへ進むことができるはずです。
「転職したいけど、自分にできる仕事があるのか不安…」
そんな方もご安心ください。
私たちジョブ活.comは 履歴書の添削や面接対策もすべて無料 でサポート。
また、都市部だけでなく地方まで、幅広い職種・業界の求人をご用意しております。

たとえ経験が短くても心配は不要。当社が厳選した企業をご紹介します。
少しでも「話を聞いてみたい」と思ったら、まずは 公式LINEに無料登録してください。
タクシードライバーに必須の「二種免許」とは?
タクシードライバーとしてお客様を乗せて運転するには、一般的な普通自動車免許(一種免許)だけでは不十分です。お客様の命を預かり、安全かつ確実に目的地まで送り届けるためには、より高度な運転技術と専門知識が求められます。そのために必要となるのが「第二種運転免許」、通称「二種免許」です。
一種免許との決定的な違いと、二種免許が必要な理由
一種免許と二種免許の最も大きな違いは、「旅客運送の対価として報酬を受け取れるかどうか」にあります。一種免許は自家用車を運転するための免許であり、お客様を乗せて運賃を受け取る営業行為はできません。一方、二種免許は、お客様を乗せて運賃を受け取る「旅客運送」を事業として行うために必要な免許です。
二種免許がタクシードライバーに不可欠な理由は、主に以下の2点に集約されます。
- 法的根拠と安全性の確保: 道路交通法により、旅客運送を行う車両の運転には二種免許が義務付けられています。これは、お客様の安全を最優先するためです。二種免許の取得過程では、一種免許よりも厳しい基準の運転技術や、お客様を安全に運ぶための知識が問われます。例えば、急ブレーキを避ける、滑らかな発進・停止、適切な車間距離の保持など、お客様に快適な移動を提供するための運転技術が重視されます。
- プロとしての責任と信頼性: タクシードライバーは、お客様の命を預かる「プロの運転手」です。二種免許は、そのプロとしての責任と信頼性を社会に示す証でもあります。万が一の事故の際にも、お客様の安全を確保するための知識や対応能力が求められるため、二種免許の取得は、お客様からの信頼を得る上で非常に重要です。
二種免許で運転できる車両の種類と業務範囲
二種免許は、その種類によって運転できる車両や業務範囲が異なります。タクシードライバーが取得するのは主に「普通二種免許」です。
【普通二種免許で運転できる車両と業務】
- タクシー: お客様を乗せて運賃を受け取る営業行為。
- ハイヤー: 事前に予約されたお客様を送迎するサービス。
- 運転代行: お客様の車を運転して目的地まで送るサービス(お客様を乗せる場合)。
- 路線バス: 路線に沿ってお客様を運送するバス(大型二種免許が必要な場合が多い)。
普通二種免許は、定員10人以下の車両で旅客運送を行う場合に必要となります。バスや大型トラックなど、より大きな車両で旅客運送を行う場合は、「大型二種免許」や「中型二種免許」が必要となるため、ご自身の目指すキャリアに合わせて取得する免許の種類を確認しましょう。
二種免許の取得条件を徹底解説
二種免許の取得には、年齢や免許保有期間、身体能力など、いくつかの条件が定められています。これらの条件を満たしているか、事前に確認することが重要です。
年齢・免許保有期間の条件
二種免許を取得するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 年齢: 満21歳以上であること。
- 免許保有期間: 普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許のいずれかの第一種免許を取得しており、かつその免許を受けていた期間が通算して3年以上(免許停止期間を除く)であること。
例えば、20歳で普通免許を取得した場合、二種免許の取得は21歳になってから、かつ普通免許取得から3年が経過している必要があります。
視力・深視力など身体的条件
安全な旅客運送を行う上で、身体的な適性も厳しく審査されます。特に重要なのが視力と深視力です。
- 視力: 両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上であること。眼鏡やコンタクトレンズを使用しても構いません。
- 深視力(しんしりょく): 遠近感を測る能力です。三桿法(さんかんほう)という検査で、3本の棒のうち中央の棒が前後に動くのを見て、他の2本と並んだときにボタンを押します。誤差が2cm以内であることが条件です。この検査は一種免許にはないため、初めての方は戸惑うかもしれません。
- 色彩識別能力: 赤、青、黄色の信号灯の色を識別できること。
- 聴力: 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。
- 運動能力: 自動車の運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。
特に深視力は、慣れないと難しいと感じる方が多いようです。事前に眼科で検査を受けたり、練習用の器具で慣れておくことをおすすめします。
過去の違反歴・行政処分に関する注意点
過去の交通違反や行政処分は、二種免許の取得に影響を与える可能性があります。
- 免許停止・取消処分: 過去に免許停止や取消処分を受けたことがある場合、その期間は免許保有期間の3年に算入されません。また、取消処分を受けた場合は、欠格期間(免許を再取得できない期間)が終了している必要があります。
- 累積点数: 交通違反の累積点数が多い場合、免許センターでの適性試験や面接で不利になる可能性もゼロではありません。
タクシードライバーは、お客様の命を預かる責任ある仕事です。過去の運転履歴も、その適性を判断する重要な要素となります。ご自身の運転履歴に不安がある場合は、事前に運転免許センターや公安委員会に相談してみるのが確実です。
二種免許の取得方法と費用・期間を比較【失敗しない選び方】
二種免許の取得方法は大きく分けて「自動車教習所に通う」か「運転免許センターで一発試験を受ける」の2通りがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。
自動車教習所(通学・合宿)で取得するメリット・デメリット
多くの人が選ぶのが、自動車教習所に通う方法です。通学と合宿の2つのスタイルがあります。
【通学教習所のメリット・デメリット】
- メリット:
- 自分のペースで通えるため、仕事や家庭との両立がしやすい。
- 疑問点があればすぐに指導員に質問できる。
- 学科・技能ともに丁寧な指導を受けられるため、合格率が高い。
- デメリット:
- 費用が高め(30万円~40万円程度)。
- 取得までに時間がかかる場合がある(1ヶ月~3ヶ月程度)。
- 向いている人: 費用よりも確実性や安心感を重視する方、自分のペースで学びたい方。
【合宿教習所のメリット・デメリット】
- メリット:
- 短期間で集中して取得できる(最短8日~10日程度)。
- 通学よりも費用が抑えられる場合がある(25万円~35万円程度)。
- デメリット:
- まとまった休みが必要。
- 一度に多くの情報を詰め込むため、集中力が必要。
- 向いている人: 短期間で免許を取得したい方、費用を抑えたい方。
教習所を選ぶ際は、自宅からのアクセス、費用、取得期間、指導員の質などを比較検討しましょう。
運転免許センターで「一発試験」に挑戦するメリット・デメリット
運転免許センターで直接試験を受ける「一発試験」は、費用を大幅に抑えられる可能性がありますが、難易度は非常に高いです。
【一発試験のメリット・デメリット】
- メリット:
- 費用が圧倒的に安い(数万円程度)。
- 自分のタイミングで受験できる。
- デメリット:
- 合格率が非常に低い(数%程度と言われる)。
- 試験官による採点基準が厳しく、一度のミスが命取りになる。
- 練習環境を自分で確保する必要がある。
- 何度も受験することになり、結果的に費用や期間がかさむ可能性もある。
- 向いている人: 運転技術に絶対的な自信があり、費用を最大限に抑えたい方。
一発試験は、一種免許の取得経験が豊富で、かつ二種免許の試験内容を熟知している方でなければ、合格は困難です。多くの場合、教習所に通う方が結果的に効率的で確実です。
費用を抑えるには?タクシー会社による免許取得支援制度
「二種免許の取得費用は高額で、すぐに用意できない」と心配な方もご安心ください。多くのタクシー会社では、未経験者向けの「二種免許取得支援制度」を設けています。
【免許取得支援制度の概要】
- 費用負担: 会社が二種免許の取得費用を全額または一部負担してくれる制度です。
- 研修期間中の給与: 免許取得期間中も給与が支給される会社もあります。
- 条件: 会社によって異なりますが、入社を前提としたり、一定期間の勤務を条件とする場合が多いです。
この制度を利用すれば、自己負担なし、あるいは最小限の負担で二種免許を取得し、すぐにタクシードライバーとして働き始めることができます。未経験からタクシードライバーを目指す方にとって、非常に魅力的な制度と言えるでしょう。求人情報を確認する際は、この支援制度の有無を必ずチェックしてください。
二種免許の試験内容と合格へのポイント
二種免許の試験は、学科試験と技能試験(実技)の2段階で構成されます。一種免許よりも専門的な知識と高度な運転技術が求められるため、しっかりとした対策が必要です。
学科試験の内容と効果的な勉強法
学科試験は、一種免許の知識に加え、旅客運送に関する専門知識が問われます。
- 出題範囲:
- 道路交通法規(一種免許の範囲に加えて、二種免許特有の法規)
- 旅客自動車運送事業に関する法令
- 運転者の心得、安全運転に関する知識
- 応急救護に関する知識
- 出題形式: 95問(文章問題90問、イラスト問題5問)で、90点以上が合格です。
- 効果的な勉強法:
- 教本を熟読する: 教習所で配布される教本や、市販の二種免許用問題集を繰り返し読み込み、内容を理解する。
- 問題集を解きまくる: 過去問や模擬問題を徹底的に解き、間違えた問題は解説を読んで理解を深める。特に、一種免許にはない旅客運送に関する問題は重点的に対策しましょう。
- アプリやオンライン教材を活用する: スマートフォンアプリやWebサイトには、二種免許の学科試験対策に特化したものが多数あります。移動時間などを活用して効率的に学習できます。
技能試験(実技)のポイントと注意点
技能試験は、一種免許よりもはるかに厳しく評価されます。お客様を乗せることを想定した、安全で快適な運転が求められます。
- 評価基準:
- 安全確認: 発進、車線変更、右左折、停車など、あらゆる場面での確実な安全確認。
- 運転操作: 滑らかな発進・停止、適切な速度維持、正確なハンドル操作、適切な車間距離。
- 法令遵守: 信号、一時停止、速度制限などの厳守。
- 旅客への配慮: 急ブレーキ・急ハンドルを避ける、乗り心地の良い運転。
- 課題走行: 方向転換、縦列駐車、S字カーブ、クランクなど。
- 減点ポイント:
- 安全確認の不足(目視を怠るなど)
- ふらつき、急ハンドル、急ブレーキ
- 指定速度からの大幅な逸脱
- 一時停止線のオーバー
- 縁石への接触
- 合格のための練習方法:
- 教習所の指導を徹底的に受ける: 指導員の指示を忠実に守り、指摘された点はすぐに改善する。
- 反復練習: 苦手な課題や操作は、納得がいくまで繰り返し練習する。
- 試験コースの把握: 試験が行われるコースを事前に確認し、イメージトレーニングを行う。
- 落ち着いて運転する: 緊張はミスを誘発します。深呼吸をして、常に冷静な運転を心がけましょう。
取得時講習(応急救護・旅客者講習)について
二種免許の学科試験と技能試験に合格した後には、「取得時講習」の受講が義務付けられています。
- 応急救護処置講習: 交通事故発生時などに、負傷者に対して適切な応急処置を行うための知識と技術を学びます。心肺蘇生法や止血法などが含まれます。
- 旅客者講習: 旅客運送のプロとして必要な知識や心構え、お客様への接遇、安全運転の重要性などを学びます。
これらの講習は、単なる形式的なものではなく、タクシードライバーとしてお客様の安全と快適さを守る上で非常に重要な内容です。真剣に受講し、実践に役立てる意識を持つことが大切です。
【最新情報】地理試験は廃止!その後の実情と影響
かつてタクシードライバーになるためには、二種免許の取得に加えて「地理試験」に合格する必要がありました。しかし、この地理試験は2014年に廃止されています。
地理試験廃止の背景と現在の制度
地理試験は、東京都、神奈川県、大阪府など一部の特定地域で実施されており、その地域の主要な道路、交差点、施設などの地理知識を問うものでした。しかし、この試験がタクシードライバー志望者の参入障壁となっているとの指摘や、カーナビゲーションシステムの普及により、その必要性が薄れたことから、2014年1月1日に廃止されました。
【現在の制度】
地理試験の廃止後、その代わりに「タクシー乗務員登録研修」や「事業者研修」といった形で、各タクシー会社や地域ごとの協議会が、ドライバーに必要な地理知識や接客マナーなどを教える研修を実施しています。これにより、より実践的な知識を習得できるようになっています。
廃止後の地域ごとの対応と注意点
地理試験は廃止されましたが、地域によっては独自の研修や講習が設けられています。
- 東京都: 東京タクシーセンターが実施する「タクシー乗務員登録研修」の受講が義務付けられています。この研修では、都内の主要な地理、法令、接客マナーなどを学びます。
- その他の地域: 各地域のタクシー協会や事業者が、独自の研修プログラムを用意していることが多いです。
タクシー会社に入社後、これらの研修を受けることで、地域の地理やお客様対応のノウハウを習得できます。入社を検討しているタクシー会社がどのような研修を提供しているか、事前に確認しておくと良いでしょう。
タクシードライバーに求められる「地理知識」の習得方法
地理試験は廃止されましたが、タクシードライバーにとって「地理知識」が不要になったわけではありません。むしろ、お客様に信頼され、効率的に業務を行う上で、依然として非常に重要なスキルです。
【地理知識の重要性】
- お客様からの信頼: 「この道で合ってる?」「もっと早く着く道はない?」といったお客様の質問に的確に答えられるドライバーは、信頼されます。
- 効率的な運行: カーナビに頼りきりでは、渋滞を避ける裏道や、時間帯による最適なルート選択ができません。地理知識があれば、お客様を最短・最速で目的地へお送りできます。
- 売上向上: 効率的な運行は、一日の乗車回数を増やし、結果として売上向上に直結します。
【効果的な地理知識の習得方法】
- 地図アプリやカーナビを積極的に活用する: 目的地までのルートをただ表示させるだけでなく、周辺の主要施設や道路の名称、一方通行などを意識して確認する。
- 実際に街を走る: 研修期間中や、プライベートの時間に、主要な駅や繁華街、観光地周辺を実際に運転して道を覚える。
- 先輩ドライバーから学ぶ: ベテランの先輩ドライバーは、生きた地理情報や裏道を豊富に持っています。積極的に質問し、ノウハウを吸収しましょう。
- 「流し」営業で実践的に学ぶ: 実際にタクシーを運転し、お客様を乗せて様々な場所へ行くことで、自然と地理知識が身についていきます。
地理知識は、経験を積むことで確実に向上します。焦らず、日々の業務の中で積極的に学ぶ姿勢が大切です。
未経験・年齢の不安を解消!タクシー会社のサポート体制と成功事例
「未経験だけど本当にタクシードライバーになれるの?」「もう〇〇歳だけど、今からでも遅くない?」
このような不安を抱えている方も多いでしょう。しかし、多くのタクシー会社は未経験者や中高年の方の採用に積極的であり、充実したサポート体制を整えています。
未経験者でも安心!充実した研修制度
タクシー会社に入社すると、二種免許取得後も、プロのタクシードライバーとして独り立ちするための様々な研修が用意されています。
- 座学研修: 会社の規則、運賃制度、地理知識(地域特有のルートや施設)、接客マナー、緊急時の対応など、基本的な知識を学びます。
- 実車研修(OJT): 経験豊富な先輩ドライバーが同乗し、実際の営業ルートやお客様対応、機器操作などを実践的に指導します。お客様を乗せる前に、自信を持って運転できるようになるまでサポートしてくれます。
- 地理研修: 地理試験は廃止されましたが、主要な駅や観光地、病院などのルートを覚えるための実践的な地理研修が行われます。
- 機器操作研修: タクシーメーター、カーナビ、決済端末、無線機などの操作方法を習得します。
これらの研修を通じて、未経験の方でも安心して業務を始められるよう、会社全体でサポートする体制が整っています。
【成功事例】50代からタクシードライバーになったAさんの話
「本当に自分にもできるのだろうか」と不安を感じる方もいるかもしれません。ここで、実際に未経験からタクシードライバーとして成功したAさんの事例をご紹介します。
Aさん(50代男性)は、長年勤めた会社を早期退職後、「新しいことに挑戦したい」という思いからタクシードライバーの道を選びました。当初は「地理に自信がない」「お客様とのコミュニケーションが不安」といった悩みを抱えていましたが、入社したタクシー会社の充実した研修制度と、先輩ドライバーの温かいサポートに支えられ、着実にスキルを身につけていきました。
特に、地理知識の習得には、研修で教わったことを元に、休日に実際に街を歩き、地図と照らし合わせながら覚える努力を重ねました。また、お客様との会話では、最初は緊張したものの、研修で学んだ「笑顔と丁寧な言葉遣い」を心がけることで、徐々に自信がつき、今では多くのお客様から「Aさんのタクシーは安心して乗れる」と高い評価を得ています。
Aさんは「最初は不安だらけでしたが、会社の手厚いサポートと、何よりお客様からの『ありがとう』の一言が、私の原動力になっています。年齢は関係ありません。挑戦する気持ちがあれば、誰でも活躍できる仕事だと実感しています」と語っています。
高齢者でも活躍できる!年齢制限の実情と求人の探し方
タクシードライバーは、年齢に関わらず長く活躍できる仕事として知られています。定年退職後にセカンドキャリアとして選ぶ方も多く、60代、70代のドライバーも珍しくありません。
- 年齢制限の実情: 多くのタクシー会社では、明確な年齢上限を設けていないか、設けていても70歳前後までとしているケースが多いです。重要なのは、健康状態と運転への意欲です。
- 経験よりも人柄: 未経験者歓迎の求人が多く、これまでの職歴や運転経験よりも、お客様への丁寧な対応や安全運転への意識といった「人柄」が重視されます。
- 求人の探し方:
- 人材紹介会社: タクシードライバー専門の人材紹介会社は、未経験者向けの求人や、二種免許取得支援制度のある会社を多数紹介しています。キャリアアドバイザーがあなたの希望に合った会社を提案し、面接対策などもサポートしてくれます。
- 求人サイト: 大手求人サイトでもタクシードライバーの求人を見つけることができます。「未経験歓迎」「二種免許取得支援あり」などの条件で絞り込んで検索してみましょう。
- 会社のホームページ: 気になるタクシー会社の採用情報を直接確認するのも有効です。
年齢を理由に諦める必要はありません。健康で運転への意欲があれば、タクシードライバーとして新たなキャリアを築くことは十分に可能です。
二種免許取得から「理想のタクシードライバー」へのロードマップ
二種免許を取得し、タクシー会社に入社することは、あくまでスタートラインです。ここからは、どのようにすれば「理想のタクシードライバー」として活躍できるのか、そのロードマップをご紹介します。
高収入を目指すための働き方とコツ
タクシードライバーの収入は、基本給に加えて歩合給の割合が大きいため、工夫次第で高収入を目指すことが可能です。
- 営業戦略を立てる:
- 時間帯ごとの需要を把握: 早朝の空港送迎、日中のビジネス街、深夜の繁華街など、時間帯によってお客様のニーズは異なります。
- イベントや天候を考慮: イベント開催時や悪天候時は、タクシーの需要が高まります。
- 効率的な「流し」: 空車時間を減らすため、お客様がいそうな場所を効率的に巡回する。
- 待機場所の選定: 駅や病院、ホテルなど、お客様が多い場所での待機も有効です。
- お客様へのサービス向上:
- 丁寧な接客: 笑顔での挨拶、荷物の積み下ろし、快適な車内環境の提供。
- 安全運転: 急発進・急ブレーキを避け、お客様に安心感を与える運転。
- 地理知識の活用: 最適なルート提案や、お客様の質問への的確な回答。
- 無線配車やアプリ配車を積極的に活用: 効率的に仕事を得るための重要なツールです。
これらのコツを実践することで、お客様からの信頼を得てリピーターを増やし、結果として売上アップに繋げることができます。
多様な勤務体系とライフスタイルに合わせた選択肢
タクシードライバーの勤務体系は多様であり、ご自身のライフスタイルに合わせて選択できるのが魅力の一つです。
- 隔日勤務: 1日働いて、次の日は休みというサイクルです。例えば、朝から深夜まで勤務し、翌日は丸一日休みとなります。月の勤務日数は11~13日程度で、休日が多く、プライベートの時間を確保しやすいのが特徴です。
- 昼日勤: 朝から夕方まで勤務する、一般的な会社員に近い勤務体系です。女性ドライバーや、夜間の運転に不安がある方、規則正しい生活を送りたい方に向いています。
- 夜日勤: 夕方から深夜・早朝まで勤務する体系です。深夜帯は割増運賃が適用されるため、効率的に高収入を目指しやすいのが特徴です。
ご自身の体力や生活リズム、収入目標に合わせて、最適な勤務体系を選ぶことが、長く働き続けるための秘訣です。
タクシードライバーとしてのキャリアアップ・独立の可能性
タクシードライバーとしてのキャリアは、単に運転するだけではありません。様々なキャリアアップの道や独立の可能性も開かれています。
- ハイヤー運転手: VIPや企業の役員などを送迎するハイヤーの運転手は、より高い接客スキルと運転技術が求められますが、高収入が期待できます。
- 個人タクシー: 経験を積んだ後、個人事業主として独立し、自分のタクシーを運営する道です。自由な働き方ができる反面、経営に関する知識も必要となります。
- 運行管理者・管理職: 経験を活かして、タクシー会社の運行管理者や営業所の管理職として、ドライバーの指導や運行管理に携わる道もあります。
- 観光タクシー・介護タクシー: 特定のニーズに特化したサービスを提供する専門ドライバーとして活躍することも可能です。
タクシードライバーは、お客様との出会いを通じて人間力を高め、自身のスキルを磨きながら、多様なキャリアパスを描ける魅力的な仕事です。
まとめ
タクシードライバーへの転職は、二種免許の取得から始まります。本記事では、二種免許の必要性から取得条件、具体的な取得方法、費用、試験対策、そして地理試験廃止後の最新情報まで、未経験からタクシードライバーを目指す方が知っておくべき情報を網羅的に解説しました。
タクシードライバーへの挑戦を迷っているあなたへ
「本当に自分にできるだろうか」「年齢がネックになるのでは」といった不安は、誰もが抱くものです。しかし、多くのタクシー会社は未経験者や中高年の方の採用に積極的であり、二種免許取得支援制度や充実した研修制度を通じて、あなたの挑戦を全力でサポートしてくれます。
タクシードライバーは、お客様を安全に目的地まで送り届けるという社会貢献性の高い仕事であり、頑張り次第で高収入も目指せる魅力的な職業です。また、多様な勤務体系やキャリアアップの可能性も広がっており、あなたのライフスタイルや目標に合わせた働き方を見つけることができるでしょう。
まずは情報収集から!おすすめの次のアクション
二種免許の取得は、あなたの新しいキャリアの第一歩です。この記事を読んで、タクシードライバーへの興味がさらに深まった方は、ぜひ次のステップに進んでみてください。
- タクシー会社の人材紹介サービスに登録する: 未経験者向けの求人情報や、二種免許取得支援制度のある会社を効率的に見つけることができます。専門のキャリアアドバイザーが、あなたの疑問や不安に寄り添い、最適な転職先を見つけるサポートをしてくれます。
- タクシー会社の採用説明会や見学会に参加する: 実際の職場の雰囲気や、先輩ドライバーの声を聞くことで、より具体的なイメージを持つことができます。
- 求人サイトで情報を集める: 「タクシードライバー 未経験」「二種免許取得支援」といったキーワードで検索し、具体的な求人情報を確認してみましょう。
一歩踏み出す勇気が、あなたの未来を大きく変えるかもしれません。ぜひ、この機会にタクシードライバーという新しいキャリアの可能性を探ってみてください。
「転職したいけど、自分にできる仕事があるのか不安…」
そんな方もご安心ください。
私たちジョブ活.comは 履歴書の添削や面接対策もすべて無料 でサポート。
また、都市部だけでなく地方まで、幅広い職種・業界の求人をご用意しております。

たとえ経験が短くても心配は不要。当社が厳選した企業をご紹介します。
少しでも「話を聞いてみたい」と思ったら、まずは 公式LINEに無料登録してください。



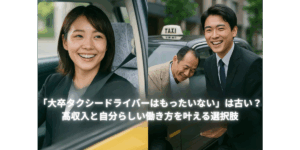




コメント